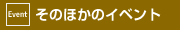2021年度マンデートーク
 月曜日の午後、テーマごとに学芸員が常設展示室を解説します。学芸員が研究する専門分野のお話から、毎週新たな発見があるかもしれません。
月曜日の午後、テーマごとに学芸員が常設展示室を解説します。学芸員が研究する専門分野のお話から、毎週新たな発見があるかもしれません。
また、マンデートークでは1回参加するごとにスタンプカードに1つスタンプを押し、参加回数に応じて素敵な記念品を贈呈します。
ぜひご参加ください。
開催日:2021年4月5日(月)~2022年3月28日(月)までの月曜日 ※祝日、年末年始、7月26日~8月31日を除く。
時間:午後1時30分~1時50分
場所:常設展示室の各階入口よりスタート
※当日の開催場所はチラシまたは受付にてご確認ください。
参加費:入館料のみ必要
【開催内容】
★第1回★
2021年4月5日(月)午後1時30分~1時50分
「オリエントの舗床モザイク」 巽 善信 学芸員
オリエントの装飾技法のなかに、モザイクがあります。簡単にその歴史を紹介するとともに、展示している舗床モザイクの画像を解説します。
★第2回★
2021年4月12日(月)午後1時30分~1時50分
「アイヌの着物」 中谷 哲二 学芸員
かつてアイヌ民族は北海道のみならず、その周辺域である本州東北部や樺太(からふと:現サハリン)・千島でも暮らしを営んでいました。この北の厳しい自然環境の中で、樹皮繊維や木綿を用いて調製された、彼らの伝統文化を代表する独創的な着物を主にご紹介いたします。
★第3回★
2021年4月19日(月)午後1時30分~1時50分
「縄文晩期 亀ヶ岡文化の話」 藤原 郁代 学芸員
1万年以上も続いた縄文時代の間に、地域ごとに異なる文化が育まれました。縄文時代晩期、東北地方では高度な技術によって美しい土器や遮光器土偶、さまざまな土製品が作られました。亀ヶ岡文化と呼ばれるその文化のいろいろな製品をご紹介します。
★第4回★
2021年4月26日(月)午後1時30分~1時50分
「メキシコ、グアテマラの織物」 梅谷 昭範 学芸員
中米のメキシコとグアテマラの村落では、現在も家庭内で衣服を手作りし、着用する伝統が受け継がれています。今回は展示品を通じて、織り技術やデザインについて解説します。
★第5回★
2021年5月10日(月)午後1時30分~1時50分
「端午の節句と厄除け」 幡鎌 真理 学芸員
端午の節句にも厄除けの意味があることをご存知でしょうか。端午に摘んだ薬草は効能が高いと信じられ、古来「薬狩」がおこなわれました。病を封じ、邪気を祓うパワーをくれる端午の節句と展示している五月人形について解説します。
★第6回★
2021年5月17日(月)午後1時30分~1時50分
「幻の貝紫染め」 梅谷 昭範 学芸員
メキシコ・オアハカ州で伝統的に織られている淡い紫色の織物は、その希少性から「幻の貝紫染め」と呼ばれることがあります。今回は染料の観点から織物を見つめ直すことで、その背景にある歴史と文化を解説します。
★第7回★
2021年5月24日(月)午後1時30分~1時50分
「台湾シラヤの壺を祀る信仰」 早坂 文吉 学芸員
台湾南部に暮らすシラヤには、壺を祀る信仰が伝えられています。“コンカイ”と呼ばれる集会所の祭壇に水を入れた壺を祀るのです。壺などの展示品を見ながらシラヤ独自の信仰をご紹介します。
★第8回★
2021年5月31日(月)午後1時30分~1時50分
「天理参考館の古越磁」 青木 智史 学芸員
越州窯は、中国の越と呼ばれていた地域(浙江省周辺)にあった青磁窯の総称です。中国を代表する青磁窯でおよそ千年に渡って長く活動しました。今回はその内の古越磁と呼ばれる古い時代に焼かれた青磁を見ていきましょう。
★第9回★
2021年6月7日(月)午後1時30分~1時50分
「バリ島トゥンガナン・プグリンシンガン村の儀礼」 荒田 恵 学芸員
バリ島の先住民が暮らすトゥンガナン・プグリンシンガン村で行われている儀礼について、当館の資料を紹介しながらお話しします。
★第10回★
2021年6月14日(月)午後1時30分~1時50分
「テル・ゼロールの発掘」 巽 善信 学芸員
日本オリエント学会は設立 10 周年事業として、1964 から 66 年にかけて、イスラエルにあるテル・ゼロール遺跡を発掘調査しました。その時出土した遺物はイスラエルと協議の上、両国で折半されました。日本側の遺物は実は本館に寄贈されています。発掘出土品ですのでその学術的価値は計り知れません。一部展示していますのでご紹介します。
★第11回★
2021年6月21日(月)午後1時30分~1時50分
「絵馬と祈願奉納品」 中谷 哲二 学芸員
絵馬の奉納は現代の日常生活にも深く根付いています。様々な絵馬や祈願奉納品がどのような意図で奉納されているのか、その願いの諸相をみてみたいと思います。
★第12回★
2021年6月28日(月)午後1時30分~1時50分
「天理市杣之内火葬墓出土の海獣葡萄鏡」 日野 宏 学芸員
奈良時代の貴族墓である杣之内火葬墓から出土した海獣葡萄鏡について、その図像や出土状況について解説します。
★第13回★
2021年7月5日(月)午後1時30分~1時50分
「大井川の川越」 乾 誠二 学芸員
江戸時代、東海道の中でも橋がなかった大井川は、箱根の山と並んで難所とされていました。いかにして川を渡ったか、資料から当時の様子をのぞいてみます。
★第14回★
2021年7月12日(月)午後1時30分~1時50分
「軒丸瓦の文様」 藤原 郁代 学芸員
日本の軒丸瓦には「○○蓮華文軒丸瓦」というキャプションがついています。なぜそんな呼び名があるのか、また文様はどのように変化していったのかをお話しします。
★第15回★
2021年7月19日(月)午後1時30分~1時50分
「台湾の寺廟の扉と龍柱について」 中尾 徳仁 学芸員
当館には、かつて台湾の寺廟で使用されていた大きな扉が展示されています。この扉に描かれている吉祥図案と、龍が彫られた石製の柱(龍柱)についてお話しします。
★第16回★
2021年9月6日(月)午後1時30分~1時50分
「キップの話」乾 誠二 学芸員
日本最古の鉄道乗車券が天理参考館にあることをご存じでしょうか。明治5年に新橋横浜間で鉄道が開業した際のエピソードを交えながら、最初のキップについて解説いたします。
★第17回★
2021年9月13日(月)午後1時30分~1時50分
「チャンスンとパガジ面」梅谷 昭範 学芸員
威嚇するような表情の顔を持つ木製の柱「チャンスン」と、ヒョウタンを素材にして作られた演劇用の仮面「パガジ面」は、朝鮮半島の伝統文化を代表する造形物です。両者の役割とその背景にある歴史について紹介します。
★第18回★
2021年9月27日(月)午後1時30分~1時50分
「潘士興肖像画から見る18世紀の台湾先住民」早坂 文吉 学芸員
潘士興は現在の台中市近郊に暮らしていた先住民、パゼッヘの首長一族の一人です。この肖像画が描かれた歴史的背景や、18世紀における台湾先住民と漢族との関わりをみていきたいと思います。
★第19回★
2021年10月4日(月)午後1時30分~1時50分
「古代中国の武器-剣・斧・矛・戈・弩-」青木 智史 学芸員
古代中国、特に戦乱の時代であった春秋・戦国時代には様々な武器が登場し用いられていました。当館には、剣・斧・矛・戈・弩といった様々な武器が展示されています。これらを通して古代中国の武器について紹介します。
★第20回★
2021年10月11日(月)午後1時30分~1時50分
「東南アジアのべテル・チューイング(ビンロウ噛み)」荒田 恵 学芸員
ビンロウは日本では馴染みのない嗜好品です。当館の資料を紹介しながら、東南アジアのビンロウ噛みについてお話しします。
★第21回★
2021年10月18日(月)午後1時30分~1時50分
「布留遺跡のまつり」日野 宏 学芸員
当館3階の布留遺跡コーナーには他に例をみない特異な円筒埴輪で囲われた祭場が復元展示されています。布留遺跡で行われた古墳時代のまつりをご紹介したいと思います。
★第22回★
2021年10月25日(月)午後1時30分~1時50分
「日本の看板と引札・ちらし」中谷 哲二 学芸員
商店の看板や広告チラシに相当する引札(ひきふだ)は、商いに関する情報を伝える道具として今も生活の中に息づいていると言えるでしょう。これらから「引きつけよう―記憶に残そう―」とする創意工夫の数々をご案内いたします。
★第23回★
2021年11月1日(月)午後1時30分~1時50分
「ペルシア陶器の美①―ペルシア三彩―」巽 善信 学芸員
イスラーム時代に今のイランの地で作られた陶器をペルシア陶器と呼びます。イスラームに入って急激に陶器が発展します。その時代背景と初期に特徴的な三彩を紹介します。
★第24回★
2021年11月8日(月)午後1時30分~1時50分
「通い徳利」幡鎌 真理 学芸員
店名が入っている徳利は、酒屋がお得意さん向けに小売り用の貸出容器として使っていたものです。時代劇で目にされたことがあるでしょうか。「通い」に込められた環境に優しいシステムについてお話しいたします。
★第25回★
2021年11月15日(月)午後1時30分~1時50分
「古墳時代の武器と武具」藤原 郁代 学芸員
古墳時代の鉄製武器と武具は、実戦用であるとともに権威を示す道具でもありました。多種多様な武器と武具を紹介します。
★第26回★
2021年11月22日(月)午後1時30分~1時50分
「子授け祈願の土人形と版画」中尾 徳仁 学芸員
かつて中国大陸の東北部では「子供を望む女性が廟にある土人形を持ち帰って祈願し、無事子供を授かるとそれを元の場所に返す」という習慣がありました。今回は子授け祈願のための土人形と民間版画をご紹介します。
★第27回★
2021年11月29日(月)午後1時30分~1時50分
「人力車」乾 誠二 学芸員
明治時代はじめに発明され、そのスピード・乗り心地から、またたく間に駕籠に取って代わった人力車についてご紹介いたします。
★第28回★
2021年12月6日(月)午後1時30分~1時50分
「漁舟“タタラ”と台湾原住民族タオの人々」早坂 文吉 学芸員
台湾南東沖の島、蘭嶼(ランユウ)に暮らすタオの人々は海の民として知られています。トビウオ漁などに使う伝統的な木造船“タタラ”とともにタオの人々の生活文化の一端をご紹介します。
★第29回★
2021年12月13日(月)午後1時30分~1時50分
「朝鮮半島の伝統的な住まい」梅谷 昭範 学芸員
歴史的に儒教の影響を大きく受けた朝鮮半島では、日々の暮らしにもその教えが反映されていました。伝統的な住まいを再現した展示を見ながら、ひとつひとつの道具に込められた意味合いや役目をご紹介します。
★第30回★
2021年12月20日(月)午後1時30分~1時50分
「陶俑からみる唐時代の装い」青木 智史 学芸員
唐の時代は、伝統的な中国文化の装いとペルシアなどからもたらされた新たな装いが融合し、様々な魅力的な服飾文化が生み出された時代でした。陶俑に表現された服飾を例にして、唐時代の装いについて紹介します。
★第31回★
2022年1月17日(月)午後1時30分~1時50分
「ボルネオの先住民ダヤック族」荒田 恵 学芸員
当館には日本では珍しいボルネオの展示コーナーがあります。展示資料をもとに先住民ダヤック族の生業や信仰などをご紹介します。
★第32回★
2022年1月24日(月)午後1時30分~1時50分
「布留遺跡の渡来人」日野 宏 学芸員
布留遺跡からは朝鮮半島の百済や伽耶からもたらされた韓式系土器が出土しています。その幾つかは布留遺跡コーナーで展示しています。最新の技術をもたらした渡来人の活動について解説します。
★第33回★
2022年1月31日(月)午後1時30分~1時50分
「琉球地方の暮らしの民具から」中谷 哲二 学芸員
鹿児島県である薩南諸島から、沖縄県の琉球諸島にいたる南北に長い南西諸島。この沖縄・奄美地方を代表する暮らしの民具である芭蕉布(ばしょうふ)や厨子甕(ずしがめ)をご紹介します。
★第34回★
2022年2月7日(月)午後1時30分~1時50分
「ペルシア陶器の美②―彩画陶器―」巽 善信 学芸員
10世紀に入ると、色鮮やかな彩画陶器が盛んに作られるようになります。カラフルでユニークな展示品を紹介したいと思います。
★第35回★
2022年2月14日(月)午後1時30分~1時50分
「日本最初の鉄道時刻表」乾 誠二 学芸員
今からちょうど150年前、明治維新の熱気覚めやらぬ明治5年に、政府が威信をかけて鉄道を導入しました。今回は仮開業時の運行時間を知らせる時刻表についてご紹介します。
★第36回★
2022年2月21日(月)午後1時30分~1時50分
「縄文時代の骨角器」藤原 郁代 学芸員
縄文時代には、鹿の角や動物の骨を利用してさまざまな道具を作りました。その用途は工具、漁具から装身具と広い範囲に及びます。特に骨角器が発達した地域であった東北地方のさまざまな骨角器をご紹介します。
★第37回★
2022年2月28日(月)午後1時30分~1時50分
「台湾の影絵人形と指人形」中尾 徳仁 学芸員
当館が所蔵する影絵人形と指人形は、20世紀前半に台湾で蒐集されたものです。これらの演じ方、および舞台や台本などについて解説します。
★第38回★
2022年3月7日(月)午後1時30分~1時50分
「庶民の雛まつり」幡鎌 真理 学芸員
春の訪れを告げる雛まつりの主役は雛人形ですが、大名家に伝わるような豪華な雛人形ばかりではありません。庶民も楽しんだ雛まつりを彩る土雛や張子の雛、その飾り方を紹介します。
★第39回★
2022年3月14日(月)午後1時30分~1時50分
「羊皮で作られた筏(いかだ)と台湾の船」中尾 徳仁 学芸員
当館1階の「アジアの海・河川コーナー」には、羊の皮で作られた筏(中国の黄河上流地域で蒐集)と、台湾の船が3点展示されています。これらについて解説します。
★第40回★
2022年3月28日(月)午後1時30分~1時50分
「展示室で出会うインドの神々」早坂 文吉 学芸員
1階のインドのコーナーではシヴァやクリシュナ、ガネーシャ、カーリー女神などヒンズー教の神々の造形を展示しています。それぞれの神にまつわる神話や、姿かたちの特徴を紹介します。
●2022年4月以降の開催予定はこちら

 HOME
HOME